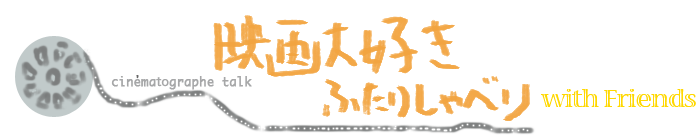
『ノーマ・レイ』 Norma Rae 1979年(アメリカ)
 監督:マーティン・リット
監督:マーティン・リット
出演:サリー・フィールド(Norma Rae役)
ボー・ブリッジス(Sonny役)
「サリー・フィールドっていいね」
マリリン:サリー・フィールドっていいね。決して美人ではないけれど、演技に強い生命力を感じる。労働者意識に目覚め、組合運動に力を入れていくノーマ・レイが「ユニオン」とクレヨンで書いた紙を掲げて立ち上がるシーンが一番好き。涙がダーッと流れました。表情がすごくいい。それから、留置所に入れられ釈放された時ワッと泣いてしまうシーンも好き。張り詰めていた思いとか屈辱とかがないまぜになって吹き出したという感じがとても伝わってくる。もう一つ、これからの自分の選ぶ道を通して起こるであろうことを、二人の子供に愛情を込めて誠実に話して聞かせるシーンも好き。親の信念を小さな子供にもきちんと伝え”誇り”ということを教える母、ノーマ・レイに胸を打たれます。アメリカ映画としては、派手さがなく、というか、どちらかというと地味に、リアルに、でいねいに作られてる感じがする。実話に基づいているらしいが、ノーマ・レイ役にサリー・フィールドを起用したのは大正解ですね。
ヤシーニ:おっしゃる通り。サリー・フィールドはこの映画でアカデミー賞とカンヌ映画祭両方で主演女優賞を受賞してるんだってね。さすがの演技、大好きです。一人の市民が権力に向かって立ち上がる時って、正義感や反骨心だけじゃなくって、きっと誰かの「愛」がその原動力になっているんだ。ノーマにとってはルーベンであり、子供たちだったような気がするね。
『女ともだち』 Le Amiche 1956年(イタリア)
 監督:ミケランジェロ・アントニオーニ
監督:ミケランジェロ・アントニオーニ
出演:エレオノーラ・ロッシ・ドラゴ(Clelia役)
ガブリエレ・フェルゼッティ(Lorenzo役)
「女優は美人だったが・・・」
マリリン:実は、分かったようで分からない映画だった(笑)。とにかくクレリアを演じた女優がものすごい美人だということだけは印象深いです。
ヤシーニ:ストーリー的にはどうなんだろうね。アントニオーニ監督は「愛の不毛」を描く人らしいのだけれど、ボクにはよく分からなかった。ただ、ここに紹介したように「どこか気になる要素」は確かにあって、それが主演のエレオノーラ・ロッシ・ドラゴの美貌なのかどうなのか? でも最初の30秒でやられちゃったのは確かだね。
『晩春』 All's Wel 1949年(日本)
 監督:小津安二郎
監督:小津安二郎
原作:広津和郎
出演:笠智衆(曽宮周吉役)
原節子(曽宮紀子役)
杉村春子(田口まさ役)
「裏切らないねえ」
マリリン:裏切らないねえ、小津さんの世界って。笠智衆も裏切らない。娘に結婚の決意をさせるために、自分は再婚すると嘘を言うあたり、父の愛情に泣かされます。永遠に変わることのない心理、真実みたいなものを日常の風景を切り取ることで描いてみせる小津映画、大好きだなあ。剥かれて帯のようになった柿の皮がポロリと落ちて笠智衆がガクっと首をうなだれる。ああ〜、切ないねえ。
ヤシーニ:小津さんが初めて「父と娘」をテーマに作った作品で、原節子とコンビを組んだのも最初。この後「麦秋」(1951)「東京物語」(1953)で原節子が演じたヒロインはすべて「紀子」で、この3作品をまとめて「紀子三部作」と呼ぶらしい。野田高悟さんとの共同脚本で、彼らのコンビは小津さんの遺作となる「秋刀魚の味」(1962)まで続くそうだ。笠智衆が演じる初老の男が娘を嫁にやる悲哀は小津作品の典型的スタイルだけど、この映画で初めて確立されたんだって。海を越えてヴィンセント・ミネリ 監督の「花嫁の父(1950)」や「かわいい配当」(1951)が、この直後にアメリカで映画化され大ヒットしているけど、小津さんのこの映画を参考にしているんじゃないってボクは思うんだよね。そういう意味でも小津さんってすごい! 笠智衆がスペンサー・トレイシー、原節子がエリザベス・テーラーって何だか面白いね。
『東京暮色』 1957年(日本)
 監督:小津安二郎
監督:小津安二郎
出演:笠智衆(杉山周吉役)
有馬稲子(杉山明子役)
信欣三(沼田康雄役)
原節子(沼田孝子役)
「」
マリリン:お待ちくださいね。
ヤシーニ:ちょっとお待ちを。
あらすじ:停年もすぎて今は監査役の地位にある銀行家杉山周吉は、都内雑司ケ谷の一隅に、次女の明子とふたり静かな生活を送っていた。長女の孝子は評論家の沼田康雄に嫁いで子供もあり、あとは明子の将来さえ決まれば一安心という心境の周吉だが最近では心に影が芽生えていた。それは明子の帰宅が近頃ともすれば遅くなりがちでしかもその矢先姉娘の孝子までが沼田のところから突然子供を連れて帰ってきたからだ。--明子には彼女より年下の木村憲二という秘かな恋人があった。母親がいない寂しさが、彼女をそこへ追いやったのだが、憲二を囲む青年たちの奔放無頼な生活態度に魅力を感じるようにいつかなっていた。しかも最近、身体の変調に気がついた彼女が、それを憲二に訴えるとそれ以来彼は彼女との逢瀬を避けるようになった。そして、焦慮した彼女は、憲二を探して回ったがその際偶然、自分の母についての秘密を知った。母の喜久子は周吉の海外在任中にその下役の男と結ばれて満洲に走ったが、いまは東京に引揚げて麻雀屋をやっていたのだ。既に秘かに堕胎してしまった明子には、これは更に大きな打撃であった。母の穢れた血だけが自分の体内を流れているのではないかという疑いが、彼女を底知れぬ深淵に突落してしまったのだ。蹌踉として夜道へさまよい出た彼女は、母を訪ねて母を罵り、偶然めぐりあった憲二の頓にさえ怒りに燃えた平手打を食わせ、そのまま一気に自滅の道へ突き進んで行った。その夜遅く、電車事故による明子の危篤を知った周吉と孝子が現場近くの病院に駈けつけたが明子は殆どもう意識を失っていた。その葬儀の母の帰途、孝子は母の許を訪れ、明子の死はお母さんのせいだと冷く言い放った。喜久子はこの言葉に鋭く胸さされ東京を去る決心をした。また、孝子も自分の子のことを考え、沼田の許へ帰っていった。雑司ケ谷の家は周吉ひとりになった。所詮、人生はひとりぼっちのものかも知れない。今日もまた周吉は心わびしく出勤する……。
『ミスター・アーサー』 Arthur 1981年(アメリカ)
 監督:スティーヴ・ゴードン
監督:スティーヴ・ゴードン
出演:ダドリー・ムーア(Arthur役)
ライザ・ミネリ(Linda役)
「執事役に注目」
マリリン:執事ホブソン役のジョン・ギールグッドがなかなかいい味を出していて泣かせる。この人、忠義・忠誠を信条とする執事の鏡という感じで、他の映画でもよく見かける。結構好き。「オリエント急行殺人事件」にも出てたな。
ヤシーニ:そうだね、あの人いいね。英国の執事をやらせたらこの人しかないって感じ。今や貴重な存在かもしれないね。いろんな役がこなせる役者もすごいけど、この役だけはやっぱりこの人でしょう、という「まるでつぶしの利かない人」ってそうはいない。日本では旅館の番頭役で大村昆というのがいたけどねえ。
『フォレスト・ガンプ 一期一会』 Forrest Gump 1994年(アメリカ)
 監督:ロバート・ゼメキス
監督:ロバート・ゼメキス
出演:トム・ハンクス(Forrest Gump役)
サリー・フィールド(Mrs.Gump役)
ロビン・ライト(Jenny役)
ゲイリー・シニーズ(Dan役)
ミケル・T・ウィリアムソン(Bubba役)
「エビと言えばババでしょ!」
マリリン:これは私たちのフェイバリット映画の一つだよね。人生に役立つ珠玉の言葉がたくさん。「バカっていうほうがバカ」ガンプのママいいこと言うね。そのとーり! 肝に銘じています。「人生はチョコレートの箱を開けてみるまで分からない」言わずと知れた名台詞ですね。「エビといえばババでしょ」・・・。何のこっちゃ? これは私たちの合い言葉みたいなもの。ガンプは、ママのお陰でちゃんと「愛」というものを知っていたんだよね。彼の生き方には愛があると思います。オープニングとラストのコントラストもいいよね。羽根が舞って、降りてきて、また舞い上がっていく・・・。音楽も素晴らしい! そうそう、ガンプの卓球の才能、スゴイ! 師と仰ぎたいほどです、はい。
ヤシーニ:もう16年も経つのかあ。何度も見た映画のひとつだな。副題「一期一会」からしてそうだけど、本当に人生の岐路に立ったとき励まされた言葉だらけだ。ダン中尉とガンプ、ジェニーとガンプ。心が傷ついている人をどうやったら救ってやれるかということをガンプは教えてくれるね。あまりにも無垢な、純粋なガンプにしかできないことかもしれないけれど、ボクらが生きていく上で参考になる教えはあまりにも多いと思うね。


『カッコーの巣の上で』 One Flew Over The Cuckoo's Nest 1975年(アメリカ)
 監督:ミロシュ・フォアマン
監督:ミロシュ・フォアマン
原作:ケン・ケーシー
出演:ジャック・ニコルソン(P.R.McMurphy役)
ルイーズ・フレッチャー(Nurse Ratched役)
ウィリアム・レッドフィールド(Harding役)
マイケル・ベリマン(Ellis役)
「昔怖かった、今難しい」
マリリン:封切られた時は中学生だったと思う。いかに映画好きだったとはいえ、意味がよく分からず、ただ怖かったのを覚えている。そのくせ、妙に強く印象に残っていた。それもそのはずジャック・ニコルソンだもんね。やっぱりあの強烈な個性は脳裏に焼き付くよね。今、この年になってちゃんと観ると、人間が人間らしくあることって何だろうかと考えさせられる。マクマーフィの反抗、そしてネイティブアメリカの患者が心を開くようになっていく過程、やがて芽生えていく友情に対して専制的体制で患者をひたすら自分たちの決めた秩序と枠の中に押し込め、人間性までも統制しようとする精神病院側の人たち。こっちのほうが困った病気だよ。人間の自由、人間の尊厳って何だろう。本当に難しい。婦長を演じるルイーズ・フレッチャー。前からこの人の顔、怖いと思っていたけど、やっぱり今観ても怖い。アカデミー主演女優賞を受賞しただけのことはあるな。ラストがまたすごくいいんだよねえ。
ヤシーニ:刑務所から逃れるために「詐病」で精神病院に入院してきたマクマーフィ。何だか「オウム裁判」のような。本当はしゃべれるのにしゃべれないふりをしているインディアンのチーフ。二人の「詐病」の物語だな。うそうそ、とにかくマクマーフィは無茶苦茶だ。婦長を殺そうとしたり、酒を持ち込んで女を呼んで精神病院でドンチャン騒ぎだもんね。最後の結末は・・・。これ、ヒットしたわけだよね。
『レインマン』 Rain Man 1988年(アメリカ)
 監督:バリー・レヴィンソン
監督:バリー・レヴィンソン
原作:バリー・モロー
出演:ダスティン・ホフマン(Raymond役)
トム・クルーズ(Charlie役)
「ダスティン・ホフマンだから」
マリリン:ダスティン・ホフマンってうまいねー。うますぎ! 私たち、実は身近で自閉症の人見てたから、レイモンドの動き、表情にかなり注目したわけね。行動パターンといいますか。ダスティン・ホフマンの演技でかなりリアリティーが保たれてると思う。彼が相当役作りの研究をしたと見た。弟のチャーリーがレイモンドに振り回されながらも、いつしか愛情を持っていくのがいい。「チャーリーとここで暮らしたい」(だったっけ?)ってレイモンドが言う最後のセリフ、泣かせるよね。ちゃんと心は通じたのでした。
ヤシーニ:精神的な病人の役ってそりゃあ難しいんだろうけど、特にこの「自閉症」は難しいだろうな。つまり、人の心が分からない人を演じるわけだからね。でも、最後は何となく心が通い合ったみたいな形にしなきゃいけない。通い合ってもおかしいし、通い合わないんじゃつまらない。通い合わせたい! そんな願望を監督も持っていたはずだし、それが十分伝わって最後はボクも泣けたんだ。
『八月の鯨』 The Whales of August 1987年(アメリカ)
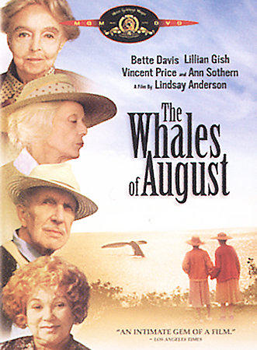 監督:リンゼイ・アンダーソン
監督:リンゼイ・アンダーソン
脚本:デイヴィッド・バリー
出演:ベティ・デイヴィス(Libby役)
リリアン・ギッシュ(Sarah役)
ヴィンセント・プライス(Mr.Maranov役)
「老姉妹の夏、せつなく」
マリリン:少女の頃から毎年繰り返されてきた、小さな島の別荘で過ごす夏。老姉妹のささやかな日常を通して、これまで生きてきた人生までもがあぶり出されるよう。お互いに頼り、頼られ生きていること、時にはそれが腹立たしかったり、うとましかったり、そして心強かったり。老いというものを実感したときにこそ、より心に深くしみるだろうと思う。寄り添うように生きている老姉妹の姿は、老いと寄り添って生きる姿そのもの。誰にも歩いてきた人生の物語があり、日々は繰り返されていくんだなあ。淡々と描かれている分、八月の鯨を見ることを今も夢見続けている老女たちが愛しくなる。サラ役のリリアン・ギッシュって撮影当時93歳だって!
ヤシーニ:田舎にいて、老人と接する機会が多いせいか、老人を扱った映画は無条件で見たくなるね。特にこの映画は渋いなあと思う。テーマはきわめて普遍的だ。老い、それは現実だから。彼女たちに八月があと幾度訪れるだろうか。そして鯨に出会えるだろうか。余談だけど、ボクらが好きな村のお年寄りの皆さん、どうか死なないでくださいね。
『肉体の悪魔』 Le Diable au Corps 1947年(フランス)
 監督:クロード・オータン・ララ
監督:クロード・オータン・ララ
原作:レイモン・ラディゲ
出演:ミシュリーヌ・プレール(Marthe役)
ジェラール・フィリップ(Fraecois役)
ジャン・ドビュクール(Fraecois's Father役)
ドニーズ・グレー(Marthe's Mother役)
「美男美女の恋愛秘話」
マリリン:美男美女が恋に落ちる、肉体の悪魔に弄ばれていく悲恋物語、いやあ、古き良き時代のフランスの恋愛映画ですなあ。
ヤシーニ:いやあ、ホンマですなあ!
マリリン:どうしたの? ちょっとテンション高くない?
ヤシーニ:そりゃあそうですわな。美男美女の悲恋物語でっしゃろ? テンション無茶苦茶高こうなりますわな!
マリリン:あんた、横山やすし?
ヤシーニ:ちゃいまんがな。ワシの名前はやなあ・・・。
マリリン:ちょっと、始めていい? 時間ないんで。
ヤシーニ:あっ、えらすんません。どうぞどうぞ。
マリリン:この映画は、夫が戦地から戻るまでのつかの間の恋と知りつつ・・・。燃え上がってはみたものの、お互いに本気で一緒になるまでの勇気がなかったりする辺りの幼さがいいんだろうな。これが酸いも甘いも分かりきった中年男女となると、やっぱり話は違うもんねえ。
ヤシーニ:そうそう、幼さゆえに燃え上がる炎ってやつ。
マリリン:ラストは、どう思った?
ヤシーニ:マルトはかわいそうではあるけど、もっとかわいそうなのは夫だよなあ。
マリリン:うんうん、一緒。最後に呼んだ名前が「フランソワ」で、しかも、彼との子どもを残して逝っちゃうわけだもの。どう考えればいいのって、ねえ。あら、私たちって現実的過ぎるかしら?
ヤシーニ:幼い恋はやっぱあきまへんわなあ。
『眺めのいい部屋』 A Room With a View 1986年(イギリス)
 監督:ジェームズ・アイヴォリー
監督:ジェームズ・アイヴォリー
原作:E・M・フォースター
出演:ヘレナ・ボナム・カーター(Lucy役)
デンホルム・エリオット(Mr.Emerson役)
ジュリアン・サンズ(George Emerson役)
ダニエル・デイ・ルイス(Cecil役)
「絵画のような映画」
マリリン:美しい、ひたすら美しい。絵画のような映画ですねえ。私、すごく好きな映画です。
ヤシーニ:何かムードがあって心に残ってる映画だね。
マリリン:この映画はね、友達のモモコちゃんのお勧めだったのよ。
ヤシーニ:へええ、あのモモコちゃんの? じゃあ、是非コメント載せてもらわなきゃだね。
マリリン:アカデミー賞の衣装賞、美術賞を取っただけのことあるわ。イタリアの町やイギリスの田舎の風景、人物も衣装も美術も、スクリーンに映し出される何もかもがうっとりするほど美しいですねえ。
ヤシーニ:ルーシーは、イギリスの階級社会の中で、良家のお嬢さんとして生きることを当たり前のように受け入れつつも、内に秘めた情熱が鳥が羽を伸ばすように次第に目覚めていく。自由に、活き活きと飛びたくなっていく。そんなルーシーをヘレナ・ボナム・カーターはとてもよく表現していたと思う。すごくかわいいよね。案外肝が据わっていたりして、たまんなくわかいい。
マリリン:いったん、同じく上流階級の、知性しか取り柄のないような味気ない青年、セシルと婚約するわけだけど、最初は当たり前にそうなるもんだと受け入れていたのよね。でも、どうみても性格違い過ぎだわ(笑)。
ヤシーニ:そのセシル青年なんだけど、妙に印象に残るんだなあ。かなりいい味出してる。
マリリン:森の中でのキス、あれ、駄目よ。味気ないって言われてもし方ないね(笑)。ふられて泣くとこも好きだなあ。結構辛らつなこと言われちゃうんだけど、大真面目に「君の言うとおりだ。僕の気づかなかった僕のこと教えてくれてありがとう」みたいなこと言うあたりがたまらない。でもやっぱ、ショックだったんだよね。階段でコケてた。
ヤシーニ:あの銀縁の眼鏡と小指、おっかしいよね。でも、いかにも上流階級の紳士って感じが出ていて、オカマチックだけど、姿がとっても美しい方だよね。
マリリン:で、ジョージは労働階級なわけだけど、なかなかこちらも素敵ですわ。あの野性的な押しの強さにひかれる気持ち、分かるなあ。ルーシーにはやっぱりこちらの方でしょう。
ヤシーニ:ジュージのお父さんに諭されて、本当の気持ちに気づいたルーシーが外で待っていた馬車(だっけ?)に駆け戻るシーン、あのキラキラ輝いた若さあふれる表情がたまらなくいいね。
マリリン:ジーンときて、思わず涙が出ちゃった。そして冒頭と同じホテルのシーン、眺めのいい部屋をめぐる会話が再現される辺り、ニクイ演出ですな。その光景をほほえましく見つめているのはルーシーとジョージでしたってとこが、これまたニクイ、ニクイ。
ヤシーニ:ニクイ、ニクイ! 何度観ても、とってもすてきな映画です。
マリリン:モモコちゃん、ありがと!
『偶然の旅行者』 The Accidental Tourist 1988年(アメリカ)
 監督:ローレンス・カスダン
監督:ローレンス・カスダン
原作:アン・タイラー
出演:ウィリアム・ハート(Macon役)
キャスリーン・ターナー(Sarah役)
ジーナ・デイヴィス(Muriel役)
エイミー・ライト(Rose役)
「アン・タイラーの人生観」
マリリン:人生にはいろいろなアクシデントがあるわけで、子どもの死という重く悲しい出来事によって、夫婦の歯車がかみ合わなくなり、別れに至る。ひょんなことから新しい恋が始まることもあれば、もとに戻りたいと思うこともある。というわけで、いろいろあるのよ、人生は。(何のこっちゃ)。で、「人生と同じで、旅も荷は軽いほうがよい」という一節がこの映画に出てきます。なかなか含蓄がありますな。
ヤシーニ:どうにもならない問題を抱えながらも生きていく、それが 人生、それが本当の生きる厳しさ、普通に生きることの難しさ。ピューリッツアー賞を受賞したアン・タイラーの人生観が凝縮したような作品だね。
マリリン:それに、コメディーではないけれど、結構笑わせてくれます。犬の調教師ミュリエルとのからみも面白いけど、私は、メーコンの家族のほうが、大真面目にとぼけてて面白かったな。
ヤシーニ:周りの登場人物がみんなちょっと曲者で、メーコン自身も実用性一点張りの男。悲しみを表に出さず、心にくすぶらせ続ける男。そんな心理描写がよく描かれていて胸に沁みる。アン・タイラーにしては珍しく、ラストがモヤモヤせずに終わっている小説の映画化です。
『夜の終わりに』 Niewinni Czarodzieje 1960年(ポーランド)
 監督:アンジェイ・ワイダ
監督:アンジェイ・ワイダ
脚本:イエジー・アンジェイエフスキー/イエジー・スコリモフスキー
出演:タデウシュ・ウォムニツキ(Andrzej役)
クリスティナ・スティプウコフスカ(Magda役)
ズビグニエフ・チブルスキー(Edmunt役)
「ポーランド映画の魅力1」
マリリン:ポーランド映画って、ひと味違うよね。不思議な雰囲気がある。
ヤシーニ:何でだろうね。1回観ちゃうとはまっちゃうんだよね。アンジェイ・ワイダって監督は不出生の天才だと思う。そんなに有名じゃないけど。
マリリン:この映画、行きがかり上、気乗りがしないままアパートにやってきたマグダだったけど、次第にうち溶け合っていく。
ヤシーニ:交わされる言葉遊びみたいな会話がとてもハイセンス、というか、ちょっぴり背伸びしているって感じが良い、良い。
マリリン:彼女、とってもキュートだよね。ヤシーニ、好きでしょ、ふふふ。
ヤシーニ:ボクはね、あんまりそういうの好きじゃないんだよ。
マリリン:うそばっか。顔に「大好き」って書いてあるぞ。
ヤシーニ:どこに?
マリリン:ほら、ここ。
ヤシーニ:あっ、ホントだ。ゴシゴシ(笑)。
マリリン:ゲームに負けて洋服脱いだら、結構デカパンだったりするのもかわいいし。
ヤシーニ:あれはブリジット・ジョーンズのほうがデカかった(笑)。
マリリン:ラストのヒネリが効いてるよね。いない、と思ったらいた、と思ったらいない、と思ったら戻ってきた、みたいな(笑)。ずーっと暗い感じでくるから(夜っていう設定のせいもある?)朝を迎えてのラストシーンは爽やかです。
ヤシーニ:そうだね。何かしゃれてるよね。あっ、そうそう、この映画サウンドトラックにジャズを使ってなかった? あれも結構効いてるかもね。オシャレだ。
『水の中のナイフ』 A Knife in the Water Noz w Wodzie 1962年(ポーランド)
 監督:ロマン・ポランスキー
監督:ロマン・ポランスキー
脚本:イエジー・スコリモフスキー他
出演:レオン・ニェムチック(Andrzej役)
ヨランタ・ウメッカ(Christina役)
ズイグムント・マラノウィッチ(The young man役)
「ポーランド映画の魅力2」
マリリン:始まりがいきなり意表をつくよね。ムーディーなジャズの調べに乗って、車が走っていく。
ヤシーニ:そっか、これもジャズだったか。
マリリン:カメラはフロントガラスをアップで真正面からとらえているんだけど、そこに映るのは景色だけで、男女の顔はほとんど分からない。これでもうやられたって感じ。
ヤシーニ:うん、何やら不穏な予感。
マリリン:倦怠期っぽいブルジョア夫婦が、ヒッチハイクの青年をクルージングに誘ったことから起こっていく3人の人間模様が描かれているわけよね。
ヤシーニ:そもそも何で? あれってヨット自慢?
マリリン:若さみなぎる青年を前に、精一杯気取って優越感にひたっているけど、逆にそれで余計にたそがれて見えてしまう中年男。哀しいわ。
ヤシーニ:大人と若者の対比がすごく上手いね。
マリリン:三角関係っていえば三角関係になるんだけど、勝手にムキになって、どんどんドツボにはまっていく中年が滑稽でもある。青年も当然、青いからムキになるわけで、一人、冷静な女が怖〜い。
ヤシーニ:時々挑発してるっぽかったりと、ちょっと刺激を楽しんでたりもするわけよね。怖い怖い。
マリリン:ヨットの上が舞台になっていたり、カップルの間に青年が挟まって、挑発したりされたりっていうあたり、「太陽がいっぱい」を彷彿とさせるよね。
ヤシーニ:何が起きるのか、時々「もしかして」とゾクッとするシーンがあるもんね。
マリリン:けんかになって、ののしり合う中で、お互い腹の中にあったことが全部出てきてしまう。「そう思ってたんだな!」「そう思ってたのね!」みたいな。怖い、怖い。
ヤシーニ:でも、結局、最後は何もなかったかのようにもとに戻っていくわけで、この辺が大人ってことだろうか。
マリリン:自分の非を認める夫に大人を感じたのかもね。
ヤシーニ:ボクはいつも非を認めてますよ。
マリリン:そうそう、大人ちゃんね。この映画、妙に後を引きます。
『約束の土地』 Ziemia Obiecana Country 1975年(ポーランド)
 監督:アンジェイ・ワイダ
監督:アンジェイ・ワイダ
出演:ダニエル・オルブリフスキ(Karol役)
ヴォイツエフ・プショニャック(Moritz役)
アンジェイ・セヴェリン(Max役)
「ポーランド映画の魅力3」
マリリン:お待ちくださいね。
ヤシーニ:ちょっとお待ちを。
あらすじ:19世紀未、ポーランド。中部の工業都市ウッジは、織維工場のメッカであった。国籍の異なる三人の若者が、協力してポーランド人の工場を作ろうと希望に燃えていた。その三人とは、三世紀にも渡るポーランド士族の末裔カルロ・ボロヴェツキ(ダニエル・オルブリフスキ)、商才のあるユダヤ人モリツ・ヴェルト(ヴォイツェフ・プショニャック)、繊維工場主を父に持つドイツ人マックス・バウム(アンジェイ・セヴェリン)だ。彼らは、旧世代の経営者に変わりウッジを支配するのだ、と誓い合いそれぞれ資金集めを始めた。まず、カロルはドイツ人社長に、モリツはドイツ人工場主に、そしてマックスは父親に金を出させるようはたらきかけた。そのころ、ウッジでは商売に行きづまった資本家たちによる保険金目あての放火が相次ぎ、中には自殺する者もいた。カルロにはアンカ(アンナ・ネフレベッカ)という美しい婚約者がいたが、事業達成までには手段を選ばない彼は、ユダヤ人工場主ツカー(イェジー・ノヴァク)の妻ルツィ(カリーナ・イエドルシック)と密通していた。そしてウッジの劇場で町の有力者たちが集まった夜、彼はルツィから極秘の情報を手に入れた。それは、アメリカからの輸入綿の関税が近々引き上げられるというものだ。三人は、この情報を基に、次の行動に移った。それぞれ資金を調達し、集まった三万ルーブルをもって、モリツがハンブルグヘ綿の買いつけに出かけた。輸入綿の関税が上ったところで、その綿を各工場に売りつけ、三万ルーブルを数倍に増やそうという狙いだった。それは見事に成功し、いよいよ、彼らの工場が建設されることになった。完成した工場のもとで、三人をはじめ、青年たちの共同事業がスタートする。そんな矢先、妻とカルロの関係を知り、さらに息子と思っていた子供がカルロの子供ではという疑いをもったツカーがカルロを訪ね、真相告白を迫った。一度は、それは嘘だというカルロの言葉を信用したツカーだったが、ベルリンに発ったルツィを追って列車に乗ったカルロを目撃した者の密告でツカーの怒りは爆発した。放火常習者に命令し遂にカルロの工場に火をつけさせるツカー。工場は全焼し、保険金を賭ていなかった彼らはそれで無一文になってしまう。その後カルロはアンカと別れ、以前より彼に想いを寄せていた工業界の大物ミュラー(フランチシェク・ピェチカ)の娘マダ(ボジェナ・ディキエル)と結婚しミュラー家を継いだ。それから数年、彼はウッジの実力者となり、モリツとマックスも功者となっていたが、若い頃新世代による変革を志した彼らは、今、旧資本家たちの中でそっくりその跡をついでいた。カルロの工場では、労働者たちのストライキが日に日に強化し、カルロの命令の下、赤旗をにぎったストライキのリーダーが銃殺されるのだった。
『灰とダイヤモンド』 Ashes and Diamonds Popiot I Diament 1958年(ポーランド)
 監督:アンジェイ・ワイダ
監督:アンジェイ・ワイダ
脚本:アンジェイ・ワイダ/イエジー・アンジェイエフスキー
出演:ズビグニエフ・チブルスキー(Maciek役)
エヴァ・クジイジェフスカ(Krystyna役)
Waclaw Zastrzynski(Szczuka役)
「ポーランド映画の魅力4」
マリリン:主人公のマチェックは愛国主義者で、祖国ポーランドの自主独立を目指し、共産党による新政府に抵抗するテロ実行員として、共産党指導者シチューカの暗殺という任務を遂行しようとするわけよね。
ヤシーニ:何だか難しそうな映画ですなあ。
マリリン:あなたも観たでしょ?
ヤシーニ:観た、観た。
マリリン:ポーランドという国が内包している悲劇っていうのは、日本人には、というか、私なんかには理解できないほど深いものがあるんだろうなあ。
ヤシーニ:私なんかにも理解できない・・・。
マリリン:占領されたり、イデオロギーによってたくさんの人が死ななければならなかったわけでね。きっとアンジェイ・ワイダ監督は、祖国ポーランドの歴史を作品の中に刻んでいるんだね。
ヤシーニ:そうそう、アンジェイ・ワイダさんって不出生の天才監督だと思うよ。
マリリン:それ、前にも聞いた。
ヤシーニ:そうだっけ?
マリリン:幸せなんてつかの間、いつも死と隣り合わせで、すべてが何だか悲しい結末しか待っていないみたいな、そんな時代だったんだろうね。
ヤシーニ:そういう時代だったんだろうね。
マリリン:殺されるシチューカだってかわいそうだよね。別に悪人じゃないんだし、反党派の息子も殺される運命だし、うん、やっぱりかわいそうだな。
ヤシーニ:あれ、可愛そうだな。
マリリン:彼、マチェックに撃たれた時、抱きついてきた形になったじゃない、すごく印象に残った。
ヤシーニ:印象的だった、うん、うん。
マリリン:最後、ごみの中で死んでいくマチェック、あなたは果たして灰なのか、ダイヤモンドなのか・・・。
ヤシーニ:あれは灰だな。
マリリン:どうして?
ヤシーニ:えっ? だってゴミの中で燃やされるんだから灰さ。
マリリン:・・・(絶句)。
『夜行列車』 The Night Train 1959年(ポーランド)
 監督:イエジー・カワレロウィッチ
監督:イエジー・カワレロウィッチ
脚本:イエジー・ルトフスキー/イエジー・カラレロウィッチ
出演:ルチーナ・ヴィニエツカ(Martha役)
レオン・ニェムチック(Jerzy役)
ズビグニエフ・チブルスキー(Staszek役)
Teresa Szmigielowna(Blonde役)
「ポーランド映画の魅力5」
マリリン:お待ちくださいね。
ヤシーニ:ちょっとお待ちを。
あらすじ:ポーランド中心部の駅から発車する夜行列車は、翌朝バルチック海岸の町に到着する汽車だった。ホームは混雑していた。そんな中を黒メガネの男が一等コンパートメント入口に近づいた。イェジー(レオン・ニェムチック)だ。彼は切符がなかったが、強引に乗車してしまった。また一方、眼の美しいマルタ(ルチーナ・ヴィニエツカ)とその恋人スタシェック(ズビグニエフ・チブルスキー)がいた。マルタはスタシェックとの愛を清算するべく旅行に出たのだ。列車が走り出すと女車掌はイェジーに十六号寝台券を与えた。が、その室にはマルタが乗っており、やむなく二人は同室することになった。スタシェックは普通車から「すぐ帰って来い」という手紙を渡したが、彼女は破り捨てていた。列車はある駅に着いた。イェジーはタバコを買いに下車した。その隙にスタシェックが窓下に来ては自分のもとに帰るよう懇願したがマルタは応じなかった。夜中、突然列車が止り警官達が乗りこんで来た。殺人犯が十六号室にいるというのだ。イェジーが連行されたが、すぐ釈放された。彼は実は医者であり、手術中患者を殺してしまい悩んでいたのだ。車内騒然の最中にマルタはカーテンの間からのぞく男を見つけ、その男から十六号室の券を買ったことを思い出し警官にしらせた。男は列車から飛び降りて逃げたが、墓地で乗客達に捕まってしまった。汽車は乗客を乗せ再び走り始めた。やがて夜が明け、次の駅に着いた。相変らずスタシェックは、マルタの窓をたたいた。と、イェジーが窓を開けたため、スタシェックは驚き列車の走るのを忘れてホームに残った。汽車は終点に着いた。イェジーはマルタに深い感慨を抱きながら妻の待つホームに降りていった。マルタもトランクを持つと静かに降り、遠くに白波のみえる砂浜を一人歩き続けていった。
『大理石の男』 Mans of Marble L'homme de Marbre 1977年(ポーランド)
 監督:アンジェイ・ワイダ
監督:アンジェイ・ワイダ
脚本:アレクサンドル・シチボル・リルスキ
出演:イエジー・ラジヴィオヴィッチ(Mateusz Birkut役)
ミハウ・タルコフスキ(Wincenty Witek役)
クリスティナ・ザコバトヴィッチ(HHanka Tomczyk役)
ピョートル・チェシラク(Michalak役)
「ポーランド映画の魅力6」
マリリン:お待ちくださいね。
ヤシーニ:ちょっとお待ちを。
あらすじ:976年のポーランド。映画大学の女子学生アグニェシカ(クリスティナ・ヤンダ)は、彼女の第1回ドキュメンタリー作品としてテレビ局で仕事をすることになった。彼女は、50年代の労働英雄の姿を描くことで、その年代の人々や周囲の状況を伝えようと思いあたり、主人公の調査のため博物館に行った。そして、その倉庫の隅で、かつて有名だった煉瓦積みエマテウシュ・ビルクート(イェジー・ラジヴィオヴィッチ)の彫像が放置されているのを発見した。ビルクートは、戦後のポーランドで最初に建設された大工業プロジェクトの建設に従事した労働者だったが、現在の消息は不明だった。そして、生き証人とのインタビューを通じて、彼女は、一人の労働者を浮き彫りにしてゆく。映画監督ブルスキ(タデウシュ・ウォムニツキ)は、当時統一労働者党員が組織したデモンストレーションでビルクートは煉瓦積みの新記録を打ち立てたと語った。マスコミは彼にとびつき、彼を描いた映画で、ブルスキも監督として新しい道を歩むことになったのだ。次に会ったミハラック(ピョートル・チェシラク)は、もと保安隊の将校で今はストリップ劇団の座長をしているが、彼はビルクートの経歴を詳しく知っていた。ビルクートは煉瓦積みのチームの班長だったが、そのデモンストレーションに参加した時、熱く焼けた煉瓦を渡された。それはサボタージュの意図だったのだが、同僚の一人が犯人として疑われた時、ビルクートは彼をかばい、共に刑務所に送られることになり、ビルクートは職も名誉も失つてしまったのだ。出獄したビルクートは、入獄中に別れた妻を探していたということだが、めぐり逢えたのかは定かでなかった。ビルクートの前妻がザコパネにいるらしいということからその町を訪ねたアグニェシカは、彼女に会った。そして、彼女の悲惨な生活と夫との再会の話に胸うたれた。しかし、主人公がみつからなくては映画は完成できないだろうということでテレビ局が、彼女の企画を没にしてしまった。困ったアグニェシカは、父(ズジスワフ・コジェン)に相談する。父は、彼女に平凡な真実こそが何よりも大切であること、映画が完成するということよりも、彼女が追求したそのものが真実だということを説明する。彼女は、ビルクートの息子がグダニスクの造船所で働いていることを知り、彼を訪ねた。ビルクートはすでにこの世になく、それ以上のことは、息子の口から聞き出せなかった。しかし、彼女はあきらめない。彼女はビルクートの息子と共にワルシャワに向かった。
『地下水道』 Kanal 1956年(ポーランド)
 監督:アンジェイ・ワイダ
監督:アンジェイ・ワイダ
原作:イェジー・ステファン・スタウィニュスキー
出演:テレサ・イゼウスカ(Daisy役)
タデウシュ・ヤンチャル(Korab役)
ヴィンチェスワフ・グリンスキー(Zadra役)
「ポーランド映画の魅力7」
マリリン:お待ちくださいね。
ヤシーニ:ちょっとお待ちを。
あらすじ:一九四四年九月末、爆撃と戦火で廃墟化したワルシャワの街。過去数年つづけられてきたパルチザン部隊による地下運動も悲惨な最終段階に達した。ザドラの率いるパルチザン中隊もドイツ軍に囲まれ、もはや死を待つばかり。そこで彼らは地下水道を通り市の中央部に出て再び活動をつづけることにした。夜になって隊員は地下水道に入った。中は広いが汚水が五十センチから一メートル半にも達している地下水道は暗黒と悪臭の無気味な世界である。隊員はやがて離ればなれになり、ある者は発狂し、またある者は耐え切れずマンホールから表に出てはドイツ軍に発見され射殺された。地下水道へ入る日、負傷したコラブ(タデウシュ・ヤンチャル)と、彼を助けて道案内してきたデイジー(テレサ・イゼウスカ)の二人も、やっと出口を見つけたと思ったのも、そこは河へ注ぐ通路と知って、落胆の余りその場に坐りこんでしまった。そのころ、先を行くザドラと二人の隊員は遂に目的の出口を見つけた。が出口には頑丈な鉄柵が張られ、爆薬が仕かけられていた。一人の隊員の犠牲で爆薬が破裂、出口は開かれた。ザドラと残った一人の従兵は地上へ出た。がこのときザドラは他の隊員がついてこないのを不審に思い、従兵に尋ねた。従兵はザドラが隊員を連れてくるようにとの命に背き、彼らは後から来ると嘘を言い、自分だけが助かりたいばかりにザドラについてきたのだ。これを知ったザドラは従兵を射殺。そして彼はこの安全な出ロまで地下水道をさまよう隊員を導くため再びマンホールに身をひそませた。
『女相続人』 The Heiress 1949年(アメリカ)
 監督:ウィリアム・ワイラー
監督:ウィリアム・ワイラー
原作:ヘンリー・ジェームズ
出演:オリヴィア・デ・ハヴィランド(Catherine Sloper役)
モンゴメリー・クリフト(Morris役)
ラルフ・リチャードソン(Dr.Austin役)
「」
マリリン:お待ちくださいね。
ヤシーニ:ちょっとお待ちを。
あらすじ:1850年のこと。ニューヨーク社交界の中心をなす富豪の邸宅が居並ぶワシントン街に居を占めるオースティン・スローパー博士は一人娘のキャサリンと未亡人の妹ラヴィニアと女中の4人暮らしだった。博士の亡妻は才色ともにすぐれた婦人だったにもかかわらず、娘のキャサリンは容貌も人並み以下で、そのうえ社交性の乏しい引っ込み思案の娘だった。それが父にとってはやりきれない一事で、日頃、この不出来な娘に対し、憐憫とも軽侮ともつかぬ態度をもって向かっていたのである。キャサリンは父に対してはまったく頭のあがらない存在に過ぎなかった。叔母のラヴィニアは日頃、キャサリンの味方役をつとめていたが、スローパー家のおどんだ空気をどうすることもできない有り様だった。1日、キャサリンは従妹のマリアンの婚約の宴に父や叔母と共に出席した。踊りの下手で美しくない彼女の相手を勤める男もなかったのに、この夜、彼女の前に立つモーリス・タウンゼンドという秀麗な青年の存在、キャサリンにとって夢かとばかり思われ、次第にこの青年の魅力に惹きこまれていった。スローパー博士はモーリスが定職ももたぬ遊情の青年であることを見ぬいていた。博士はモーリスが娘に求婚したと聞くとはげしく反対し、娘が彼を忘れるようにと欧州旅行に伴って行く。しかし、6カ月の旅行もキャサリンの気持ちを変えることはできなかった。博士はモーリスが望んでいるのは娘でなく、娘の財産以外の何物でもない、もし娘がモーリスと結婚するなら相続権を棄てたものと覚悟するようにと言い放つ。キャサリンは一切を棄ててもモーリスと結婚しようと決意する。だが、迎えに来てくれるはずの青年は遂に現われなかった。キャサリンはモーリスが西部に去ったことを聞いて、彼を憎むとともに、父にも深い恨みの心を抱いた。父娘の間にどうすることもできぬ溝のできたまま、スローパー博士は肺炎で急逝した。ワシントン街の邸宅はキャサリンの思いのままとなり、5年過ぎた。その夏のある日、ラヴィニアが西部から帰ってきたモーリスを伴ってきた。彼は尾羽打ち枯していたが、野心満々たる様子だった。モーリスは5年前の違約を深く詫び、彼女が自分のために莫大な遺産を失うことを見るに忍びなかったこと、いまなお彼女を愛していることを告白した。キャサリンは5年前彼に与えようとパリで購めた高価なカフス・リングを渡して、今晩訪ねてくるようにと言った。モーリスはその夜再びスローパー家の扉を叩いた。キャサリンはその音を聞きながら身動きもしなかった。彼女にはモーリスが5年前のように、自分の財産を欲しがったばかりか、今はなお愛情まで手に入れようと同じ嘘をいっていることをはっきり知っていたのである。
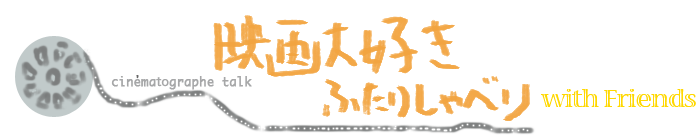




 『映画コーナートップ』
『映画コーナートップ』
 監督:マーティン・リット
監督:マーティン・リット
 監督:ミケランジェロ・アントニオーニ
監督:ミケランジェロ・アントニオーニ
 監督:小津安二郎
監督:小津安二郎
 監督:小津安二郎
監督:小津安二郎
 監督:スティーヴ・ゴードン
監督:スティーヴ・ゴードン
 監督:ロバート・ゼメキス
監督:ロバート・ゼメキス


 監督:ミロシュ・フォアマン
監督:ミロシュ・フォアマン
 監督:バリー・レヴィンソン
監督:バリー・レヴィンソン
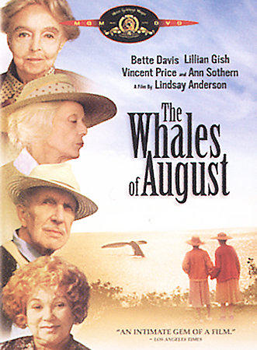 監督:リンゼイ・アンダーソン
監督:リンゼイ・アンダーソン
 監督:クロード・オータン・ララ
監督:クロード・オータン・ララ
 監督:ジェームズ・アイヴォリー
監督:ジェームズ・アイヴォリー
 監督:ローレンス・カスダン
監督:ローレンス・カスダン
 監督:アンジェイ・ワイダ
監督:アンジェイ・ワイダ
 監督:ロマン・ポランスキー
監督:ロマン・ポランスキー
 監督:アンジェイ・ワイダ
監督:アンジェイ・ワイダ
 監督:アンジェイ・ワイダ
監督:アンジェイ・ワイダ
 監督:イエジー・カワレロウィッチ
監督:イエジー・カワレロウィッチ
 監督:アンジェイ・ワイダ
監督:アンジェイ・ワイダ
 監督:アンジェイ・ワイダ
監督:アンジェイ・ワイダ
 監督:ウィリアム・ワイラー
監督:ウィリアム・ワイラー